投資信託って種類が多すぎて、どれを選べばいいか迷ってしまいませんか?
初めての投資信託選びでは、なんとなく人気商品や銀行・証券会社のおすすめに飛びついてしまい、後で「こんなはずじゃなかった…」と後悔するケースが少なくありません。
私自身も最初は右も左もわからず、毎月分配型や高コストのファンドで「なんとなくよさそう…」と選んでしまった経験があります。でも、選び方の基本を知っていれば、初心者でも安心して自分に合ったファンドを選べるようになります。
この記事では、投資歴11年の私が「失敗しない投資信託の選び方」を7つのステップで解説します。これを読めば、今日から自分の基準で商品を選べるようになるはずです。
そもそも、つみたてNISAと投資信託って別物!?
楽天証券など、証券会社のサイトを見ると「つみたてNISA」と「投資信託」が別メニューで並んでいます。
そのため、初心者の方は「これは全然別物なのかな?」と思ってしまうかもしれません。
でも実は、両者はしっかりつながっています。
- つみたてNISA → 国が用意した「投資信託を非課税で長期積立できる制度」
- 投資信託 → 実際にその制度の中で買う“商品”
イメージすると、つみたてNISAは“マイボトル”、投資信託はその中に入れる“飲み物”。つまり、つみたてNISAを使って選ぶ対象は投資信託なんですね。
🔍投資信託選びの前に知っておくべきこと
投資信託は「多くの人から集めたお金を、専門家がまとめて運用する仕組み」です。
銀行預金とは違い、元本保証はありません。つまり、増える可能性もあれば減る可能性もあります。
ここで大事なのは、投資信託を「なんとなく」ではなく目的に沿って選ぶことです。
この後の7ステップは、すべて「目的から逆算して選ぶ」ための流れになっています。
📝ステップ1 投資の目的をはっきりさせる
投資をする前に「何のために資金を増やす必要があるのか」を明確にした方が絶対にいいです。例えば…
- 老後資金
- 子どもの教育資金
- マイホームの頭金 など
すべて逆算で考えるとイメージしやすいです。
例えば老後資金について。単純計算ですが、65歳まで働くとして100歳まで生きると仮定します。35年間を毎月25万円で生活するとすると、我が家の場合は年金が夫婦で20万円ほどと推測。そうすると毎月の不足分は5万円。すると必要なお金は5万円×12か月×35年=約2,100万円になります。
数字にすると「えっ、そんなに…!」と思うかもしれません。でも、これはあくまで一つの目安です。
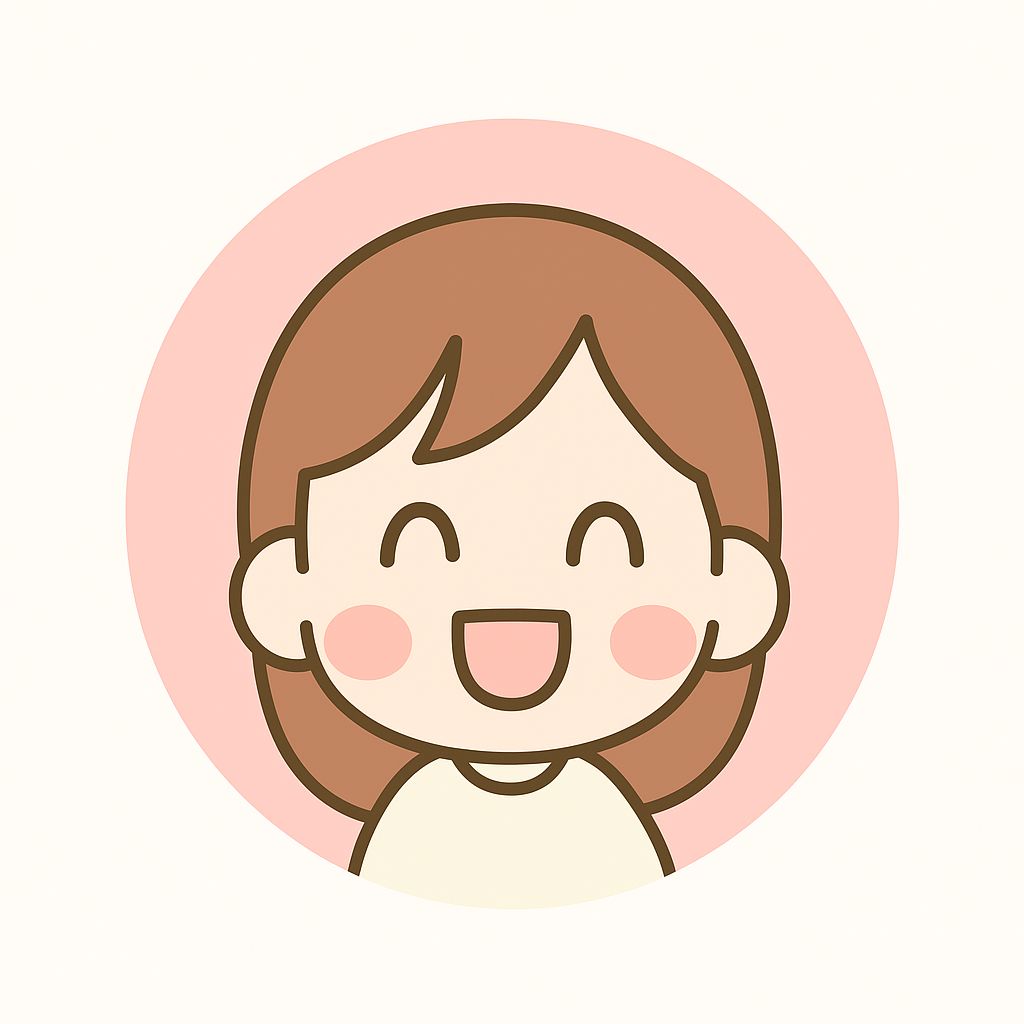
「大金を一気に用意しなきゃ…」と思う必要はありません。
退職金やすでにある貯蓄、そしてこれからの積立を組み合わせれば、40代・50代からでも十分に準備できます。大切なのは“自分の家庭に合った金額”を知ることなんです。
私も最初は「なんとなく増えたらいいな」と漠然と考えていたので常に不安でしたが、ライフプランを立てるだけでも気持ちがぐっと楽になりました。
🟢ステップ2 投資できる期間を決める
投資期間の長さによって選ぶ商品は変わります。
- 長期(10年以上) → インデックスファンドなど安定的な資産形成向け
- 中期(3〜10年) → バランス型や債券型も選択肢に
- 短期(〜3年) → 値動きの少ない商品を選ぶ方が安心
短期だと値動きが気になってストレスになりがちですが、長期投資は「放っておいても育つ」強さがあります。
私も10年以上コツコツ積み立ててきて、「気づいたら資産が育っていた」経験をしました。投資は「長期でじっくり育てる」ほうが精神的にもラクだと実感しています。
🟡ステップ3 リスク許容度を考える
投資信託は「リスク(値動きの幅)」と「リターン(増える可能性)」がセットになっています。
- 株式100%のファンド:長期的には伸びる可能性が高いけど、短期的には30%以上下がることもある
- 債券中心のファンド:増えるスピードはゆっくりだけど、大きく下がるリスクは少ない
つまり「リスクを取れば大きなリターンの可能性があるけど、心臓に悪い(笑)」ということなんです。
私は初心者の頃、毎日のように基準価額をチェックしては「下がってる!」と不安になり、一喜一憂していました。
でも少額から積み立てていくうちに、「あ、下がってもまた戻るんだ」と自然に慣れていきました。
👉 ポイントは「生活に支障のない金額で始めること」。
「最悪ゼロになっても生活できる」と思える金額からスタートすれば、心に余裕を持って投資を続けられます。
🌍ステップ4 分散投資できる商品を探す
投資信託には大きく分けて以下の種類があります。
- 株式型(成長重視)
- 債券型(安定重視)
- バランス型(株と債券を組み合わせ)
- REIT型(不動産投資信託)
私は本格的に投資を始めたとき、セゾン投信のバランス型を選びました。
理由は「世界中の株と債券に分散投資している安心感」があったから。
初心者さんにもおすすめできる選択肢だと思います。
💬 ポイント
初心者の方は、まずは世界株やバランス型など「広く分散」されているファンドを選ぶと安心感があります。
📉ステップ5 手数料を確認する
長期投資では「コストの差」が積み重なって大きな違いになります。
信託報酬がほんの0.5%高いだけでも、30年後には100万円以上の差がついてしまうんです。
例えば、毎月3万円を年利5%で30年積み立てた場合:
- 信託報酬0.5% → 約 2,241万円
- 信託報酬0.1% → 約 2,403万円
その差はなんと 約162万円。
同じ商品に投資していても、コスト次第でここまで結果が変わります。
手数料はリターンを削ります。手数料は運用期間が長くなるほど、資産を大きく目減りさせてしまうんです。
- 信託報酬は年0.1%以下を目安にする
- 購入時の販売手数料はゼロ(ノーロード)を選ぶ
「同じ投資をするなら、なるべくコストは低く!」を鉄則にしています。
また、金融機関選びも手数料に直結します。
銀行や店舗型の証券会社では、販売手数料が高かったり選べる商品が限られているケースが多いです。
一方で、ネット証券なら低コストのインデックスファンドが豊富に揃っているので、長期投資を前提にするならネット証券を使う方が有利といえるでしょう。
📊ステップ6 純資産総額や運用歴を見る
短期的に人気が出ただけのファンドよりも、5年以上安定して運用されているものが安心です。
私は投資信託を選ぶ際の1つに「純資産が右肩上がりで増えているか」も目安にしています。
たとえば私が保有している「eMAXIS Slim 先進国株式インデックス」は、2017年の設定以来ずっと純資産が伸び続けています。
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス(除く日本) | 投資信託 | 楽天証券
こうした安定感が、長期投資では大切なんです。
💡ステップ7 投資方針と自分の価値観を照し合わせる
投資信託を選ぶとき、数値や実績ばかりに目が行きがちですが、実は**「自分が安心して続けられるかどうか」**がとても大切です。
- 値動きが激しい商品だと落ち着かない
- 毎日の基準価額チェックで一喜一憂して疲れてしまう
- 長く続けられるイメージが持てない
そんな状態では、どんなに良い商品でも続けることが難しくなります。
私自身も、最初は「リターンが高いものが正解!」と思って選びましたが、実際には値動きの大きさに不安になり、結局続けられなかった経験があります。
そこから学んだのは―― 「自分の価値観に合った投資方針を選ぶことが一番の安心につながる」 ということでした。
たとえば、
✅「堅実にコツコツ増やしたい」なら → 国内債券やインデックスファンド中心
✅「多少のリスクを取っても将来のリターンを大きくしたい」なら → 株式比率高め、またはアクティブファンド
✅「毎月の分配金が欲しい」なら → 分配型ファンド(ただし税金やコストに注意)
など、自分のライフスタイルや価値観に照らして選ぶことが大事です。
投資のゴールは人それぞれ違います。
私の場合は「大金を築くこと」よりも、「お金の不安から解放されて、心豊かに暮らせること」。
そんな自分なりの答えを持っておくと、商品選びに迷ったときの道しるべになりますよ。
🌱まとめ
✅投資信託は「目的」から逆算して選ぶことが大切
✅7ステップを順番にチェックすれば初心者でも迷わない
✅最初は少額で始めて、経験を積みながら自分の基準を作っていく
我が家の場合、大金持ちになりたいわけでも、子どもに大きなお金を残したいわけでもありません。
お金の不安から解放されて、家族が心豊かに暮らせればそれで十分だと思っています。
具体的には、毎月の生活費を心配せずに払えて、年に何回かは家族で旅行や時々外食を楽しめる。そんな“小さな幸せ”を守れることが、私たちにとってのゴールです。
若いころは「もっと稼がなきゃ!」と焦る気持ちもありましたが、今では“お金に追われない暮らし”こそが一番の贅沢だと実感しています。
投資信託選びも同じで、失敗しないためのポイントさえ押さえれば大丈夫。
私自身も最初はたくさん失敗しましたが、それでも続けてきたからこそ今の安心があります。
今日の小さな一歩が、将来の大きな安心につながります。
この記事が、あなたの投資信託選びのヒントになれば嬉しいです。
一緒に“自分に合った投資信託”を見つけていきましょう。
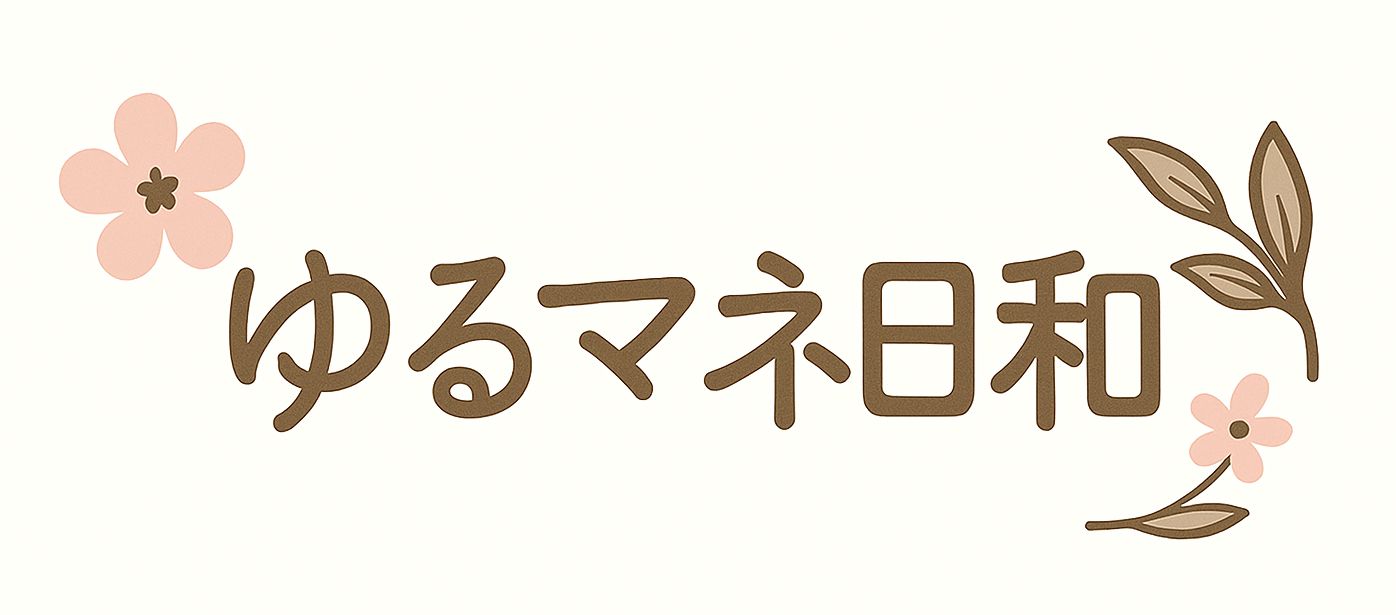

コメント